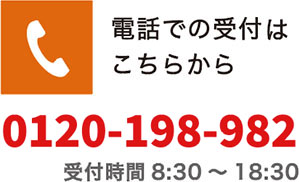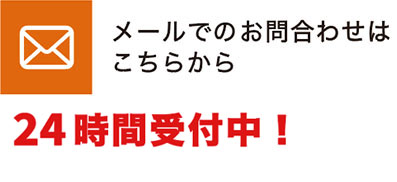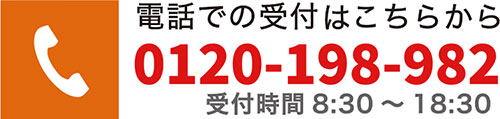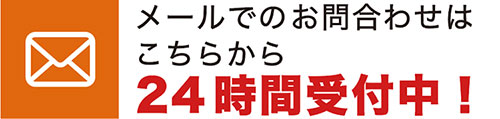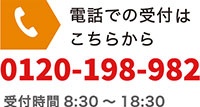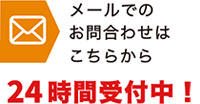2020.7.21

高崎市で日本瓦屋根のお宅を調査しました。
一見問題ないように思えますが、近くで見てみましょう。

まず屋根の一番高いところにある大棟と、屋根の隅に向かう隅棟の様子。
写真だと微妙かもしれませんが、隅棟の半円状の冠瓦が少し浮いているように見えます。

同じ隅棟を角度を変えて見たところになります。
やはり半円状の冠瓦は真っ直ぐではなく蛇行したような状態になっています。
しかも冠瓦の下にある板状の、のし瓦も本来真っ直ぐに整えて積み上げられていなければならないのですが、バラバラにずれています。
このような場合、積雪時の雪の重みによる変形が考えられます。

のし瓦の下には漆喰が塗られているのですが、その漆喰の下から何かがしみ出てた形跡が見られます。
おそらく漆喰の内側に塗られているはずの塗り土だと思われます。
本来はこのように流れ出てこないように漆喰が守ってくれるはずなのですが、漆喰の劣化により隙間が生じて、そこに雨水が入り込むようになって流れ出るようになったと考えられます。

隅棟の先端側、鬼瓦付近では茶色い塗り土の流出がはっきりとわかります。
塗り土には粘土などが含まれますが、年数経過とともにボロボロになってしまいます。
そのことが棟の形の崩れや雨漏りの原因となる場合があります。
このような状態になった場合は南蛮漆喰を使って棟の積み直しをした方が良いです。